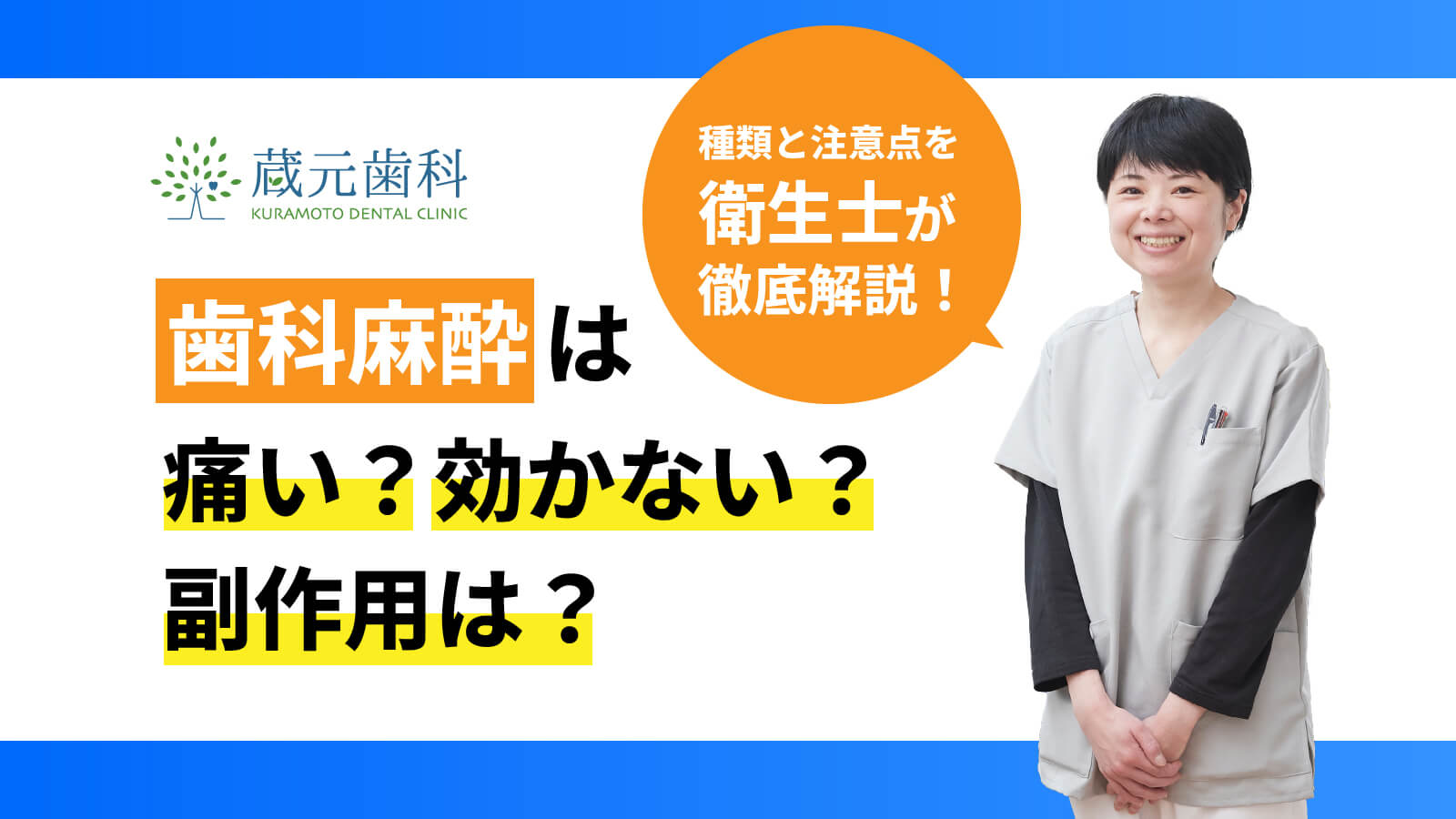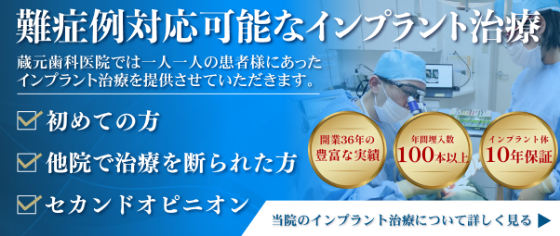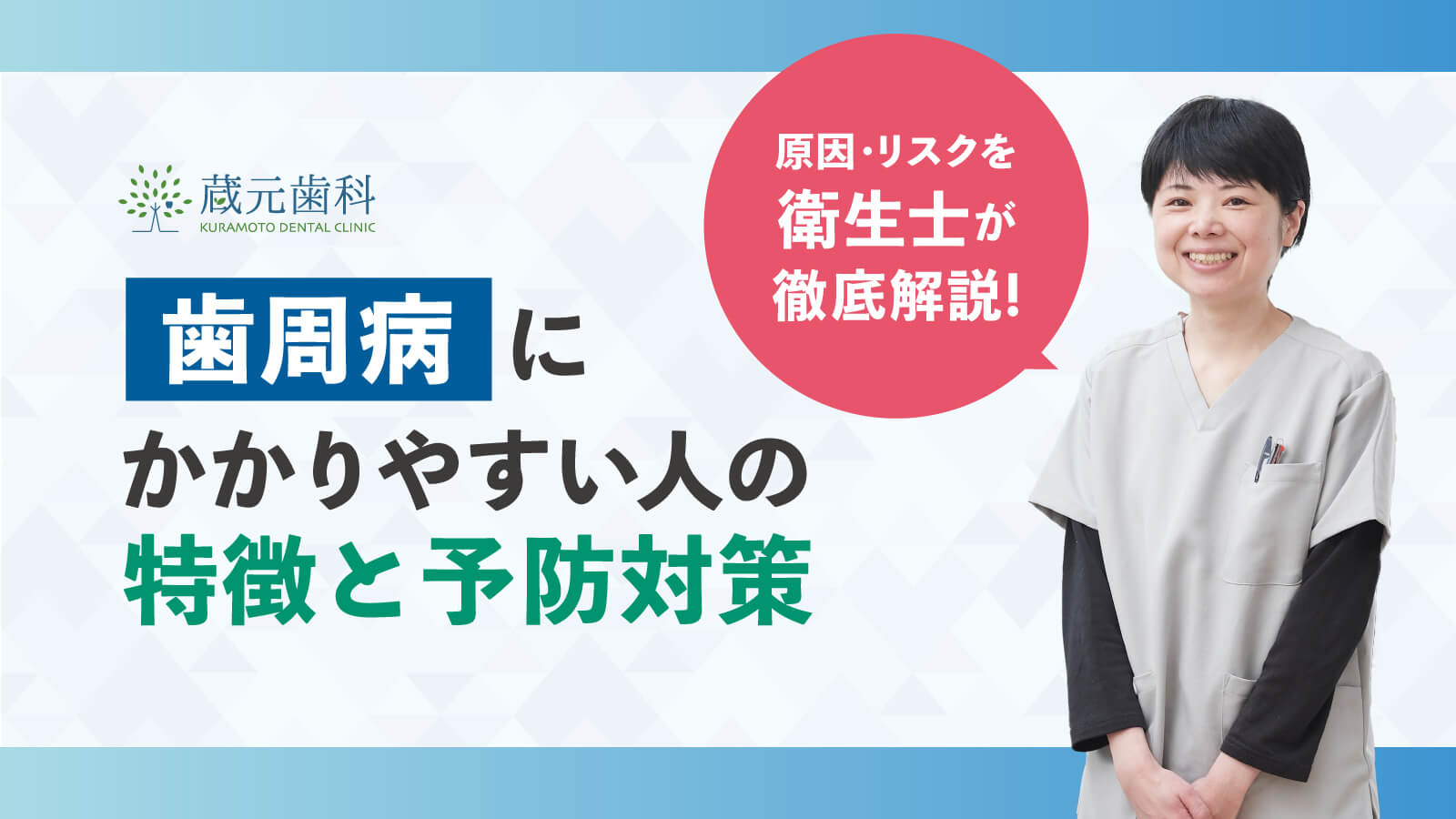
2025.07.21
歯周病にかかりやすい人の特徴と予防対策|原因・リスクを衛生士が徹底解説
こんにちは、衛生士の蔵元です。
「しっかり歯を磨いているのに、なぜか歯ぐきが腫れる…」「毎回の歯科検診で歯周病を指摘される…」そんな悩みを抱えていませんか?
実は、歯周病は“かかりやすい人”とかかりにくい人がいます。これは単に「歯みがきのうまさ」だけでなく、生まれつきの体質(遺伝)や生活習慣、口内にすみついている細菌の種類など、さまざまな要因が複雑に絡み合っているからです。
この記事では、歯科衛生士である私・蔵元が、
・歯周病にかかりやすい人の特徴
・歯周病の原因となる細菌の種類や増え方
・歯周病を防ぐために今すぐできる予防対策
などを、プロの視点からわかりやすく解説していきます。
「私も歯周病予備軍かも…?」と不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。原因を知り、対策すれば、歯周病は防げる病気です。
歯周病のかかりやすさは人によって違う?

まず、歯周病にかかりやすさが人によって違います。
歯周病はバイオフィルム細菌による感染症です。
バイオフィルムの攻撃力と歯周組織の抵抗性のバランスが均衡している時には何も起こりません。
バイオフィルムの病原性が高くなると、あるいは歯周組織が弱くなれば、均衡バランスが崩れて歯周病が発症します。
均衡バランスを決めるのは、バイオフィルムの病原性(定着した歯周病菌の種類と菌量)と歯周組織の抵抗性(遺伝と生活習慣)です。
口腔清潔が不良な場合でも、歯周組織の抵抗性が強く歯周病が発症しない場合があれば、口腔清掃が良好でも、歯周組織の抵抗性が弱く歯周炎を起こすこともあるなど、人によってさまざまです。均衡バランスを崩す要因はいくつもあり、要因が多いほど歯周病になりやすいのです。
要因のうち、歯周病菌の種類と患者さんの遺伝は変えられません。しかし、菌量と生活習慣は変えられます。
それらの要因を改善すれば、歯周病になりやすい人でも発症を予防できます。
歯周組織の抵抗性を下げる要因
生まれつき弱い免疫力、口呼吸、加齢、生活習慣(喫煙、ストレスなど)、唾液量の低下
バイオフィルムの病原性を上げる要因
悪玉歯周病細菌、磨き残した古いバイオフィルム、歯肉からの出血、タバコの科学物質、口呼吸
バイオフィルムにはいろいろな種類の細菌がいます
歯にくっつく細菌の塊をバイオフィルム(プラーク)といいますが、このバイオフィルム細菌には悪玉菌と善玉菌がいます。
どれがいるかは人によって違います。まず、悪玉菌がいない人は一安心。悪玉菌には「極悪」と「ちょい悪」がいて、極悪菌がいる人は歯周病が重症化しやすくなり、ちょい悪菌しかいない人の歯周病はマイルドです。
それでも、磨き残しが多いと、ちょい悪菌の菌量が増えてマイルドではすまなくなります。
歯周病はバイオフィルム細菌による感染症です。
だから、バイオフィルムにどんな細菌がいるかはとても大事。
歯周病菌には「極悪菌」から「ちょい悪菌」まで10種類以上もあり、病原性がまったく違います。
ちょい悪菌はほとんどの人の口の中にいますが、すべての極悪菌が揃っている人は4割程度ではないかと考えられています。一方、歯周病菌がいない人も1割程度いるようです。バイオフィルムの細菌種パターンは十人十色で、指紋と同じくらい個人差があります。
バイオフィルムの細菌は生まれた時から口に棲み始め、成長にともない定着した細菌の種類が増えていきます。
最初はお母さんの細菌がうつり、続いて他の家族からの唾液感染を受けます。そして友達、やがてパートナーからの唾液感染によりバイオフィルムの細菌の種類が決定され固定されます。
何歳で固定されるかは個人差が大きくはっきりしないのですが、30歳くらいではないかと推測されています。
バイオフィルムに一度棲みついた極悪菌は、抗生物質や抗菌剤を使っても追い出せません。
しかし、極悪菌がいる人でも、セルフケアと歯科衛生士によるプロフェッショナルケアをうまく組み合わせれば、歯周病の発症・再発は防げます。
歯肉からの出血の有無によって病原性は変わります
歯周病菌にとって欠かせない栄養素は鉄分とタンパク質です。血液はこの2つをたっぷり含んでいます。歯茎に炎症が起きて出血が始まると、歯周病菌は栄養を得て激しく暴れ出します。
そのため、バイオフィルムの毒素は高まり、歯周病が発症・進行します(均衡バランスの崩壊)。
極悪歯周病菌が生きていくためには、鉄分とタンパク質が不可欠です。
血液はヘム鉄をたっぷり含む「赤血球ヘモグロビン」と良質の「血漿タンパク質」を含んでおり、血液という最高栄養を得た極悪菌は大きく毒素を高めます(均衡バランスが大きく崩れる)。
しかし、歯茎が健康だったり、出血がない状態を保っていれば、極悪菌は栄養を摂れません。この栄養不足の状況下では、極悪菌の毒素は低いため、歯周病は起こりません(均衡バランスが保たれている)。
バイオフィルムに極悪菌が棲みついても、栄養さえ与えなければ歯周病の発症は防げます。
歯磨きでバイオフィルムを100%落としきれる人は多くはいません。
磨き残すところはいつも決まっていますから、365日磨けてないところがあるわけです。
磨き残されたバイオフィルムにいる細菌は、じわじわと毒素を高めていきます。
やがて、均衡バランスが崩れ始め、歯周組織に炎症が起きて歯茎からの出血が始まります。
歯磨きで血が出ると、歯ブラシで歯茎を傷つけたと思うかもしれません。
しかし、そこで歯茎の傷を治し出血を止めようと歯磨きを控えたり、軟らかい歯ブラシに替えると、磨き残しが増えて歯茎の炎症は悪化し、かえって出血が増えます。
歯を磨いて血が出るのは歯茎に炎症が起きた証拠です。
自己流で対処するより、すぐに歯科医院を受診しましょう。
また、口呼吸も要注意。口が開いているとバイオフィルムが乾燥し硬くなり、磨き残しやすくなるからです。
まとめ
このように歯周病のかかりやすさの要因はいくつもありますが、やはり大事なのはセルフケアです。
歯科医院でうける定期的プロケアはそのサポートです。
毎日のセルフケアでバイオフィルムを取り除き、歯周病菌の菌量を減らしましょう。